


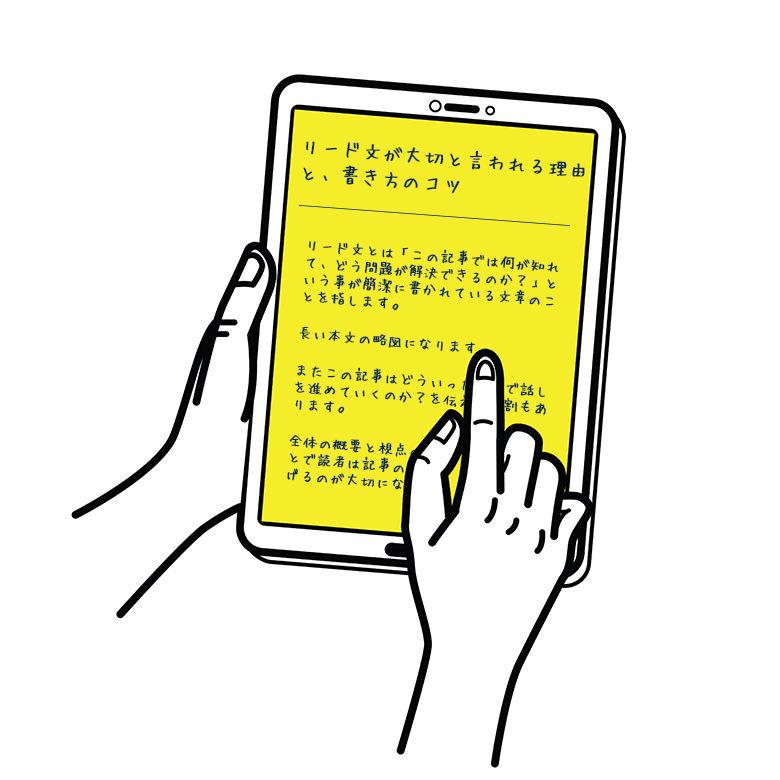
リード文とは「この記事では何が知れて、どう問題が解決できるのか?」という事が簡潔に書かれている文章のことを指します。長い本文の略図になります。
またこの記事はどういった視点で話しを進めていくのか?を伝える役割もあります。全体の概要と視点の2つを意識することで読者は記事の全容を把握させてあげるのが大切になります。
箱の中身が分からない状態で「手を入れて下さい」と言われても、怖くて躊躇する人が多いと思います。しかし中身が見える状態で安全であると自分で判断した場合には躊躇なく手を入れることができます。
リード文も同じで、記事の中身を明確にすることで読者に躊躇なく読み進めてもらうための大切な役割があります。
質問として多いのが「んー簡略化するのは分かるんだけど、具体的にどうすればいいの?」という内容ですが、これはどんな事に困っていて、どういう解決策があるのか?を考えれば解決します。
この記事では『読者を引き込むテクニック』と『やってはいけないパターン』を主に説明していきます。
この記事の目次
どの記事でもゼロから説明して書き始める人はいませんよね?これは書かない方がスマートだからです。
新車を購入してくれた運転歴20年以上の人に、ここがアクセルで、こっちがブレーキです。なんて説明したら「バカにしてるのか?」と怒られてしまいそうです。
新しく追加された新機能や、前とは違う機能から説明を開始するのが適切です。文章も同じで何から話始めればいいのか?考えていきましょう。
この2つのテーマで記事を作るとすれば、二の腕を知りたい人には鍛え方を、糖質制限無しと検索する人にはレシピや適した食材を紹介する所から説明するのが良いでしょう。
括弧書きで『共感させる』と書きましたが、共感させて本文に引き込むという流れを見出しで表したかったからです。具体的には下記の3つの方法です。
それ意外だった!面白い!と言えるような雑学に近い『知識』は読者の興味関心をくすぐることができます。
例えば
『銀杏の葉は防虫効果があるので、本の栞として昔から使われています。』
『虫喰いのない古文書には全て銀杏の葉が挟まっていたんです。』
『新幹線の名前は3つあって、こだま、ひかり、のぞみです。』
『新幹線は音速を表すこだま、光速を表すひかり、それらを超えたいのぞみの3つの名称があります。』
※名前の由来は諸説あるようですが、これが1番好きです。
どちらも後者の方が説得力がありますし『これは面白い!』と思ってもらえます。読者を掴む役割をしています。
ただし、1つのリード文に1つと決めておきましょう。これ以上書くと知識を見せびらかすようで逆効果です。
ここで前述にあった共感を生む表現はどんなものか?を説明していきます。
生活するうえで小さな不自由や不満を感じると、ネットで検索しませんか?そこで見つける『同じ悩みを持った人(記事)』に対して「私もそうなの!」「同じ悩みだから私にも合うかも!」と共感する人は多いです。
さらに、「じゃあその解決策を3つ教えます。」などのざっくりした解決策を提示することで『なになに?知りたい知りたい』と強い興味で本文に誘導することができます。
この流れを知ってはいても、できていない人は多いので再確認しておきましょう。
記事に書かれている方法は簡単か?難しいか?を表しておくと「それなら私でもやれそう」「難しそうだけど効果ありそうなので見てみる」と判断ができるようになります。
また難易度と聞くとが低い方がいいに決まっていると思われがちですが、テーマによっては難易度が高い方が信用してもらえる場合もあります。
『ダイエットは短い期間で動かなくてもがいいような手軽さを求める読者が多い』
『アトピーなどは手軽な方法よりも、長期でもより確実性のある情報を知りたい』
※後者は筆者の経験でもあり20年以上アトピーに悩んでいるので、悩みがとても深く真剣だからです。
Googleが提供するキーワードプランナーの数値を見ればどちらが多いのか?というのは分かってもらえると思います。(下記画像参照)

難易度を示すには色々な方法がありますが、
数字を使う例
失敗談を引き合いに出す
先程も書きましたが、検索者が欲している難易度に合わせて書く、という事をしっかりと把握した上で使い分けれたら脱初心者と言っても良いと思います。
ここからは、リード文でやってはいけないパターンをご紹介しています。やったら絶対記事を読まれない。とまでは言いませんが、記事の信頼を落とすことになるので「大丈夫かこの記事?」と不審に思われてしまいます。
特にやめて欲しいと思うリード文のパターンを紹介します。※全てNG例です
『日焼け対策として日焼け止めを使うことで、UVカットができるのでその選び方と使い方をご紹介します。』
前半の内容は、大人であればほとんどの人が知っていることです。それをわざわざ説明する必要はありません。
『アトピーは掻かなければ悪化もせず完治します。』
医療に関する内容は必ず裏付けが必要です、これが事実なのであれば証明できる情報元を一緒に記載してください。「言い切り」の表現の方が説得力があるという内容を履き違えています。
『鼻の周りや頬に、ぽつぽつと小さなそばかすが広がることがあります。そばかすをテーマにした歌もありますし、チャーミングなものですよね。』
繫がりが無く突拍子が無い表現になっているので違和感を感じる読者が増えてしまいますので、無理に知識を入れるのは控えましょう。
『お食い初めは、一生食べ物に困りませんようにと願いを込めた行事で生後100日を目安に今なお続く伝統文化です。ちなみに歴史ある伝統文化は他にもあり◯◯、◯◯◯、◯◯◯のうちの1つがお食い初めです。』
『ちなみに』以降は、本来のテーマとは違っているので知りたいと思っている人は少なく、書き手の知識を見せびらかせたいエゴになってしまいますのでやめましょう。関係ある話題で繋げていきましょう。
リード文だけに限らず、記事全体を通して注意したいポイントでもあります。
テーマから読者はどこまで知っているのか?を推測する
やってはいけない4つのパターン
理想は記事を書きながら調整していくことですが、それは難しいので一旦書いてから文章を寝かせてからチェックしていくのがおすすめです。