


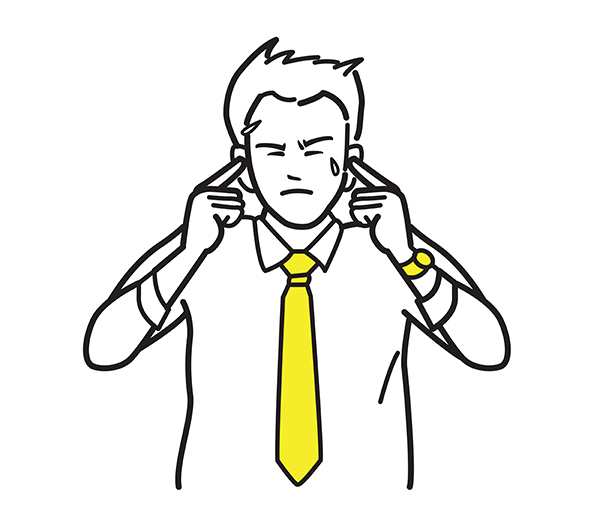
助詞とは、言葉の間をつなぐ短い単語のことで、付属語と呼ばれていてそれだけでは活用ができないのが特徴です。言葉で説明すると分かりにくいのですが、下記のような言葉と言えば分かりやすいかと思います。
「は」、「が」、「に」、「へ」、「の」、「で」、「も」、「ので」、「から」
使い方を間違えると意味が変わってしまったり、何の話をしているのか分からなくなったり、文章を書くうえで大切な働きをします。
| 逆上がりができない | 「逆上がり」はできないけど、「前回り」はできる表現 |
|---|---|
| 逆上がりもできない | 「逆上がり」はもちろん、「前回り」もできない表現 |
| 逆上がりしかできない | 鉄棒は「逆上がり」しかできない表現 |
たった1文字を変えるだけで同じ言葉を使った文章でも、意味が変わってきます。だからこそ正しい意味になるような使い方を覚えておいた方が良いです。
実際にライターさんとのやり取りの中で出た例を見ながら覚えていってください。
助詞には、格助詞、副助詞、接続助詞、終助詞という大きく4つの分類がされていますが、格助詞と接続助詞の両方に属するばあいもあるので、そこまで意識して使う必要はありません。
こういう意味なんだということだけ覚えていってください。
『と、が』、『で、を』のセットで使うことが多く、主語と述語の関係性を明確に表す助詞のことになります。また『が』の前にくる言葉が主語になります。
おばあちゃんと犬がベンチで水を飲んでいます。
ここで主語となるのは『犬』になりますが、『おばあちゃんと犬が』とワンセットになっているので、このセットが主語になります。(誰と誰が)
そして、述語である水を飲んでいる様子を表すのが後半です。「飲んでいます」何を?『水を』どこで?『ベンチで』、にかかる主語が『おばあちゃんと犬が』になります。
言葉にするととても分かりづいですが、主語と述語がおかしくなってるよ!と言われた時には、言葉の並びがちゃんとしているかチェックしてみください。
『は』『など』『だけ』『まで』『とか』などが使われていて、他の助詞に差し替えたり、助詞をとったりしても大きく意味が変わらない助詞です。ただ、最初の例同様に若干の意味が変わってきます。
唐辛子だけを食べない → 唐辛子を食べない
図書館に行くなどして、休日を過ごす。 → 図書館や公園に行って、休日を過ごす。
特別限定したい場合には、『だけ』という強調の意味もこめて使い分けていきましょう。また後半の例のようにあまり意味を変えたくない場合には、文章に『など』に該当する『公園』という言葉を足して表現すると分かりやすいです。
『ので』『ば』『と』『ても』『けれど』
前後の文章が独立して活用語となる文章につかうことが多いです。2つの『文』を繋げる役割と思って間違いありません。
接続助詞を使うことで、より表現度の高い文章になります。言い回しに困ったときには接続助詞を探して1文で使う言葉を選ぶのも良いでしょう。
『足が痛い』『先を急ごう』という2つ文を繋げてみます。
足が痛いけれど、先を急ごう。 → 足が痛いのは確定しているけど、先を急ぐ。
足が痛いので、先を急ごう。→足が痛いから、早く帰りたい意思が見られる文面
記事全体の流れに応じて使い分けると自然で、流れの良い文章になります。
『か』『よ』『ね』『もの』
副助詞と似たような役割があり、言葉に沢山の表情をつけてくれます。
明日は晴れですよ。→確定していること
明日は晴れですか。→未定・疑問の状態
明日は晴れですね。→並行(今日と同じで晴れですねの意)
文の終わりにつく助詞で「明日は晴れです」という言葉の形を一切変えずに複数の表現に繋げることができます。
普段自然に使っているので、終助詞を使っているという意識は無いかもしれませんが、文の流れの意味に合わせて使い分けてください。
基本的な依頼は「です。ます。」での指定が多いかもしれませんが、本当にです。ます。だけで文章を作成していくと単調な記事になってしまいます。
文章にリズムを出すためにも、意識的に助詞を使うようにしてみください。今まで知らなくてもこの記事を読んで、「実践してみよう」という方が1人でも増えれば嬉しいです。